カウンセリングを扱うのであれば、誰かに「カウンセリングっていうのは何がどうなって“効く”のですか?」「カウンセリングって結局“何”ですか?」と質問されたら答えられなくてはいけない。
初心者、初級者を除いて。
私なら今、「カウンセリングとは言語的または非言語的な手段を使って、他人を支援し、行動の変容を図る人間関係のことです」と答える。
何のことはない國分康孝氏の受け売り、パクリだ。
言葉としては。
この文章の意味や背景、カウンセリングの説明で、30分や1時間は話すこと、話せることがある。
長く話せば良いというものではないが、色々と考えていること、思うところがある。
あとは、それが他人の腑に落ちるか、普遍的な要素がどれだけ含まれるかが鍵になる。
私が挙げた(國分氏の文の)定義の前半「言語的または非言語的な手段を使って」という部分はこのブログでも何度か取り上げた「メッセージコントロール」に当たる。
古典>近・現代>最新(メッセージコントロール)《カウンセリングの変遷》 | deathhacks
それと、閉ざされていたり、限定的な時間や空間、条件などにも縛られないという風に解釈している。
要は何を使ってもいいということだ。
極論をすれば「手段は選ばない」、と言うか「手段はそれほど重要ではない」
非社会的なもの、非倫理的なものなどを除いては。
後半の「行動の変容を図る人間関係」について。
「行動の変容を図る」という部分については、國分氏の著書での説明が実に腑に落ちる。
カウンセリングによってクライアントの思考や世界の見え方が変われば、今までと違う行動ができるようになる。
また、周りからは「あいつはまったく変わらない」という風に見えたとしても、本人の内面が変われば同じ環境、同じ出来事に対しても、我慢ができたり、別の考え方をして人生を乗り越えていける。
そんな感じの説明だったと思うが、詳しくは本をみて欲しい。
「人間関係」については以前に述べた私の考えのエントリにリンクしておく。
カウンセリングの中で出てくる言葉のやり取りだけに注目しているならば、なぜ同じことを言っても感じ方や結果が違うのかがうまく理解できない。
意識して再現性を高めることができなくては、カウンセリングの科学性や学問性を肯定することができない。
そういう状態では、自分が良いカウンセラーになることはできても、他人にカウンセリングを上手に教えたり、継承して再生産していくことができない人だということになる。
どうも前にも書いていることを繰り返してテーマにしているが、まだまだ理解と説明の熟成が不足しているから、何度でも考え続けている。
2012-02-29 07:00



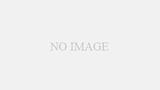
コメント