カウンセリングとは良い人間関係のことである
言ってしまうと、良い人間関係さえあれば、それがカウンセリングであるかないかは大した問題ではない。
何を話すとか、何時間かけるかとかは実はささいな違いに過ぎない。
では良い人間関係とはどういうことか。
クライアントの側から見れば、「良い」というのはカウンセラー(相手)を好きである、信頼・信用しているということになる。
好きであると言うと、恋愛を思い浮かべるかもしれないが、ここでの「好き」はいわゆる異性間の愛情というよりも性別が特別には関係しない好意と捉えている。
つまり、カウンセラーがクライアントに好かれていればそのカウンセリングはうまくいく(確率が高くなる)。
十分に好かれていなければ、いくら「良い」アドバイスをしても効果は少ないし、認知だ論理だをこねくり回しても時間やエネルギーの無駄が多い。
テクニックを論じてもピンぼけになる。
好かれるためには同じであると同時に違わなくてはいけない
では、好かれるためにはどうすればいいか。
そのために必要なのは、クライアントと価値観を共有して、同じ様に考え、感じると“同時に”、違う価値観も併せ持ち、示すことだ。
例えば、話は違うように思うかもしれないが、良くある雑誌アンケートや会話風に、「あなたは彼(彼女)のどこに惹かれたのですか?」と、その人のパートナーや恋愛対象に対する思いを聞いてみるとしよう。
「優しいから」、「経済力があって頼れる」や「関係が先にあったから」というものもあるだろう。
しかし、「価値観が似ていたから」という答えはとても多いのではないだろうか。
同じ物が好き、同じ趣味を持っている、同じことをして笑える、などなど。
一方で、「自分とは全然価値観が違っていたので(好きになった)」、「一緒にいると意外な発見があって飽きない」という意見も少なくないのではないか。
この二つの考え方は一見矛盾している。
はてさて、人間は自分と同じものが好きなのか、違うものを好むのか。
これは両者とも同時に持っていて当然の感覚なのだろう。
ストレス(変化・刺激)と同じで、まったくなければ退屈だが、常にそれがあっても疲れるし嫌になる。
あとは「同一」と「違い」のバランスとタイミング、順番の組み合わせや運命なのだろうと思う。
もう一度、恋愛を例えにして話せば、「考え方が理解できなくて、こんな人を好きになると思わず、最初は嫌いだったのにそのうちに好きになった」というマンガもあるし、「同じ趣味だし、好みも近かったから付き合ったけれども、だんだん行動や発言の小さなズレが気になってきていつしか嫌いになっていた」という物語もあるわけだ。
クライアントがピンチであるほど同じ価値観がカウンセリングのベース
我々はカウンセリングの基礎的な関係づくりを「まず味方になる」と教えている。
これはクライアントが抱えているものが大きなトラブル、重大なピンチであることを想定している。
もちろん、軽い悩みや、専門的なアドバイスがとにかく必要という状況もあるし、一緒に考えを整理するだけで落ち着く場合もある。
しかし、様々なリスクを考えると、まずは「価値観を共有して好かれる」ことを目指すことが適切と考える。
その上で、バランス・タイミング・順序などを確かめ、探りながら、違う価値観(カウンセラーの価値観)も出していく。
違う価値観を示すことは必須ではないが、必要なかったり、デメリットしかないということではない。
むしろ、それを出さなくては「良い人間関係」はできにくい。
しかし、カウンセラーの価値観を押し出すことが目的ではないし、自分と相手が基本的に対等な恋愛関係とは違い、原則としてカウンセラーはクライアントに嫌われてはいけない。
それが「良い人間関係」そのものを核としたカウンセリングだ。
2011-08-16 08:00


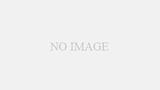
コメント