先日、自殺対策に関する教育講演を2回した。
聴衆はそれぞれ100人と50人くらい。
メンタルヘルスやカウンセリングの専門家はほとんどいなかったが、それぞれの現場では自殺企図を持つ人間に接する機会が多いという背景があった。
講演は概ね好評に終えた。
本当はこういったプレゼンテーションをする前に色々と勉強しておいた方がいいのだが、今回は講演の後しばらく経ってから「裸のプレゼンター」(ガー・レイノルズ、ピアソン桐原)を手にとった。
これまでもプレゼン技術に関するいくつかの本や文章を読んできた。
限られているけれど、教育や実技指導、講演やアップルストアでのプレゼンなどを見てもきた。
「裸のプレゼンター」はそれら過去の知識をベースに持ち、実際に数十人規模の聴衆へのプレゼンをした後には、より一層腑に落ちた。
今後数回、同書から引用してコメントし、まとめておきたい。
まずはp.33(第2章「準備」を再優先する;目的を見極める)から
プレゼンターたちは、スピーチの目的は情報を提供し、自己アピールすることだと考えていたに違いない。しかし、その目的設定は間違っていた。真の目的は、「話し手は私たちの声にきちんと耳を傾け、何を求めているのか理解してくれている」という印象を聴衆に与え、彼らにとってのメリットをはっきり示すことだったのだ。
これなどは、正にカウンセリングやコーチングにも通じる秘けつだ。
情報、つまり話の内容は大事だ。しかし、内容を話し手の完全主導で押し付けるようにしては聴衆はいい気持ちはしないから拒絶的になる確率が高くなる。
自己アピールについては私もまだうまく消化してうまく指針を決められない。
私が教育や講演を指導するとしたら「内容をアピールするのではなく、あなたというキャラクターをプレゼンしなさい」と言うし、自分にもそう言い聞かせるようにしているからだ。
もちろん毎回場面や状況、聴衆によって変化させる必要がきっとある。
大事なのは程度であり、自己アピールですら相手や聴衆本位で思いやり、配慮するということなのだろう。
聞き手が「何」を知りたがっていて、それを知ることにより何が変わってどんな「メリット」があるかを、プレゼンターが良く分かっていることを何よりもまず優先してプレゼンし、その状態を最初から最後までキープすることは難しくてチャレンジングだが、必ず目指すべき目標である。
2011-08-10 08:00



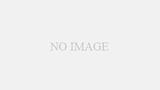
コメント