愛するだけならば、「愛」が何かを知っている必要はない。
自分の中の愛情の存在を意識する必要すらない。
「愛」を他人に伝えるならば、愛を表現できなくてはいけない。
少なくとも、対象となる相手にとって理解できるように。
カウンセリングで「自責」を説明するには「愛」についても説明できなくてはいけない。
これこそ、自分一人が理解できる理論ではダメで、できるだけ多くの人・クライアントに「ハマる」ような説明システムを複数数多く身に付けて自由に出し入れできるようにしておく。
「愛」の定義については以前のエントリ(スタバへの愛 | deathhacks)でも触れ、関連情報を紹介した。
再び引用しておく。
それでは、愛って何だろう?
哲学的かつこそばゆい疑問であるが、この設問に対し、最近やっと言語化に成功したのでここで披露することにする。
愛 = 未知なるものへの好意
Love = Favor to the Unknown”
この定義から逆を言えば「理由がある好意は『愛』ではない」。
「ここが好きだ」とか、「お金がある」から異性を好きになるとか、「自分を守ってくれる」「自分を好きでいてくれる」などの理由から来る「好き」は愛ではない。
それは「恋」とも言えるし、「計算」「打算」と呼んだほうがいいだろう。
もちろん、ここまで厳密にしてしまうと巷には純粋100%の「愛」が存在しなくなってしまう。
この定義は、「愛」を突き詰めて、純粋培養したらどういうものかという論理実験に過ぎないかもしれない。
別に100%純粋に愛しあう必要や義務はない。
ただし、カウンセリングや教育で「自責」を扱い、その背景に存在する「愛」を考え、説明するには自分の中のそれらに対する概念や理論に向き合い整理しておくべきだろう。
でなければアウトプットは適切にできない。
あと、「自責」のすべてに「愛」が関係しているわけでもないことに注意。
2011-09-10 10:00


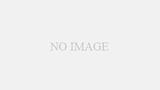
コメント