原始時代にうつはなかった。
心身ともに疲れきった状態での行動に、感情面からブレーキをかけるうつ的なものが長期間存在できなかったからである。
疲労困憊したら自然環境に負けたり獣に襲われたりして即座に命を落としていたから。
痛みや疲れというものは人にとって原則、嫌なもの、ないほうがいいもの、忌み嫌われる感覚だろう。
自分自身がそれで苦しんでいるときには「いったい何処のどいつが、なんだってこんな嫌なものを作りやがったんだ!」とでも言いたくなる。
しかし、こういった「ブレーキ」がないと、生き物は際限なくエネルギーを使ってしまったり、危険を適切に認識して避けたり、対策をしようとしたりはしなくなってしまう。
それでは、個としても集団としても不利になってしまう。
まあ、ここでは人間という種が、必要に応じてその性質を手に入れたのか、それとも元々そうした特徴を持ったグループが残って繁栄したのかとかいう進化論的な話はとりあつかわない。
疲労しきってしまったときに、動かない(動きたくなくなる)とか、動けなくなる、休む、などというのはハイリスク、ハイリターンであり、状況によっては究極の選択と集中だろう。
繰り返しになるが、人間が個としても集団としても、周りから比べれば相対的に弱小である場合には、ちょっと怪我をしたり、疲労したりしただけでも、生存を脅かす危険度は一気に上がり、閾値を越える可能性が高い。
こうした場合に有効な戦略は、慎重な行動などに向かうものではなく、メリハリの効いた、一か八か、一発逆転のものだ。
しかしながら、現代社会では、そこまで極端に変容したり、過剰に防御的になることはかえってマイナスが大きくなる。
これを、ブレーキなどの「誤作動」だと表現することもある。
長命になることによって「がん」という病気の危険や重大さがぐんぐんと上昇していることや、飢えに対抗するためにエネルギーを蓄える能力に秀でていたことが肥満や糖尿病をもたらしていることも基本的には同じ考え方でせつめいできる。
こういった考え方は即、科学的に正しいとか、論理的だとかいうものではないが、基礎的な研究や事実をつないで物事を本当に理解するための物語として重要だ。
2012-05-08 08:00
(関連エントリ)
(関連書籍)
人はどうして死にたがるのか 「自殺したい」が「生きよう」に変わる瞬間posted with amazlet at 12.05.08下園 壮太
文芸社
売り上げランキング: 173676
Posted from DPad on my iPad



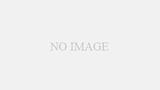
コメント