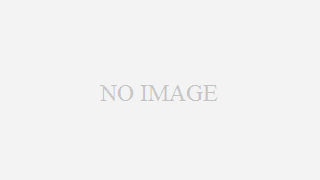 エッセイ
エッセイ iPhone5sの充電には純正microUSB-Lightningアダプタを使う
Lightning - Micro USBアダプタ - Apple Store (Japan) 付属しているUSB-Lightningコードを使うのも良いが自分はもっぱらアダプタを使っている。 アダプタを使うことの利点は、 コードが破損して...
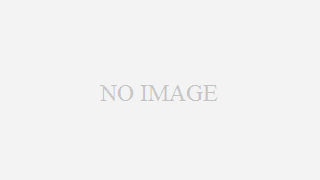 エッセイ
エッセイ 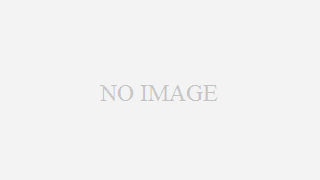 コミュニケーション
コミュニケーション 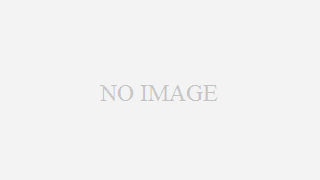 メンタルヘルス
メンタルヘルス 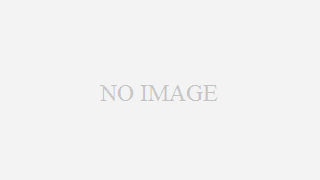 ポストベンション
ポストベンション 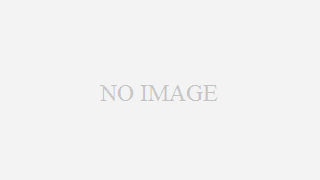 ポストベンション
ポストベンション 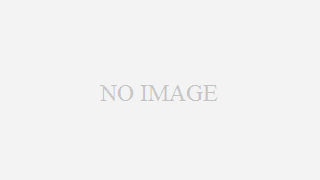 エッセイ
エッセイ 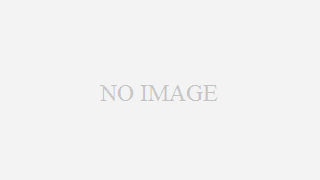 メンタルヘルス
メンタルヘルス 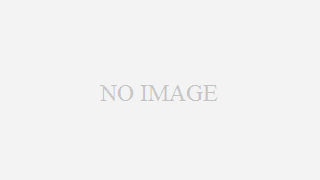 カウンセリング
カウンセリング 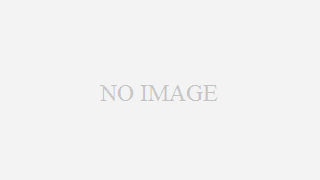 カウンセリング
カウンセリング