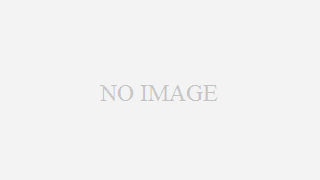 エッセイ
エッセイ 相手が年末年始をどう過ごすのかをなぜ質問するのか
この時期(2012年12月下旬)「年末はどうするんですか?」という質問をよく耳にするし、尋ねられる。 単純に他人の動きに興味がある。 自分の過ごし方を話すための枕として。 帰省することの楽しさや困難さなどを共有したいという心理から。 あるい...
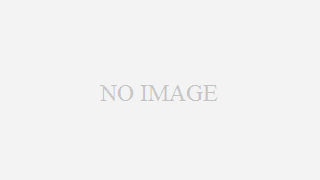 エッセイ
エッセイ 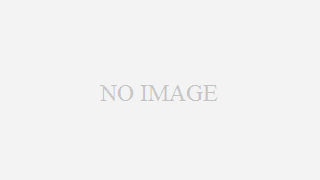 ポエム
ポエム 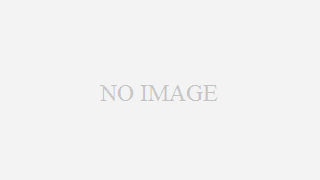 コミュニケーション
コミュニケーション 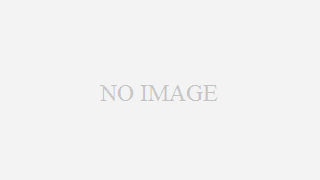 カウンセリング
カウンセリング 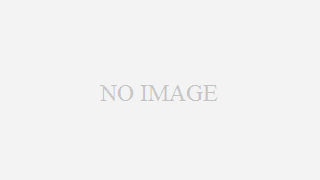 コミュニケーション
コミュニケーション 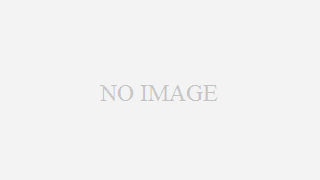 エッセイ
エッセイ 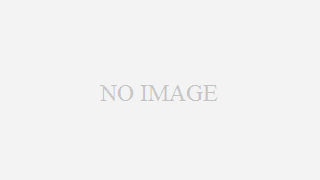 カウンセリング
カウンセリング 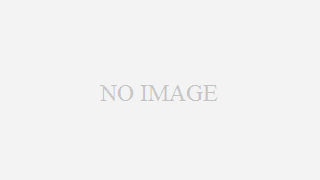 知的生産
知的生産