うつや自殺の兆候教育というものは、ずいぶんとスタンダードになった。
政府行政も、メンタル不調者をなるべく早い段階で見い出し、医療や専門家につなげるためには、職場や学校、家庭などに「ゲートキーパー」を育成することをすすめている。
もちろんこうした地道ながらボトムアップ的に、一般や社会の知識を啓蒙していくことは短期的に成果は出にくいかもしれなくても、結局は最短距離であり、もっとも効果的な方策の一つだろう。
しかし現実として、ゲートキーパーとしての役割がうまく機能しなかったり、当事者が困難を強く感じていたりする。
自殺した人の兆候を事前にまったく感じずショックを受けたり、死にたいくらいの苦しさを持って休養していた人が身近に戻ってきた後に日常的にどう接していけばいいのか不安に感じたりするケースは少なくない。
私としては、うつや希死念慮のサインを一般の多くの人に教育することには、ある程度以上のメリットはないと思うし、相当に注意が必要だと思っている。
それでは、なぜゲートキーパーがうまく機能しないのか。
そこに3つの壁があるからだ。
1 気付けない
いくら知識を身に付けたとしても、日常の生活や仕事のかたわらで、どれだけ関心があるにしても、家族や同僚の内面の変化や苦しさに的確に気づくことはやはり難しいと言わざるを得ない。
日常的に一緒に過ごしているからこそ、少しずつの変化には慣れてしまい、合算としてはおかしな事象でも「フツー」見えてしまうことも多いだろう。
正常性バイアスもかかる。
メンタル不調の表現は、個々によってかなり違う部分もあるから、専門家の研究教育でない、一般層への啓蒙では必ず「気付けないこともある」という免責的な視点を提供するべきだろう。
2 気づいても声がかけられない
仲間に何か異変を感じたとしても、即座に声をかけられるかどうか。
気のせいではないか、相手が迷惑に感じるのではないか、今は気持ちが落ちていても彼/彼女なら必ず元気に復活してくるはずだから見守るだけにしよう、以前にも同じようなことはあったから大丈夫だ、自分の方が大変だし、考え違いであったら恥ずかしい、などなど様々な心理的ブレーキがかかる。
一部には、無邪気なキャラクターで心配やコミュニケーションを取ってサポートできる人もいるだろうが、それはレアな存在とみるべきだ。
一般すべてにそれは要求できない。
3 声をかけても本人は否定し、止まらない
声をかけて、異常な状態を本人が認め、なんらかの具体的な支援を頼まれるとか、医療あるいは専門家などにつながるなどハッピーな展開となれば、こんなに喜ばしいことはない。
メンタル不調者が出ると、さも皆や管理者の失敗であるかのように思い込まれることが多いが、世の中に自殺やうつは常にあった。
数の大小やその社会的影響に上下はあっても、これからも事故や病気と一緒で完全になくなることはないだろう。
その前提で言えば、不調や不具合が見つかって、休養するパターンに持ち込めることは大成功なのだ。
病気休暇や休職に「成功」などという言葉を使うと、当事者や人事担当者からはお叱りを受けるかもしれないが。
話はそれたが、多くの場合、一度や二度、声かけをしても心配された本人は仕事や動きを簡単に止めたりはしない。
他人からの指摘で客観的に自分を見つめなおして、冷静に調整をできるようならば、元々自分でコントロールできているだろう。
そして一部のコントロールを残念ながらできなかった者が、日常を一時的に続けられない状態にまで陥っていく。
すべての者ではないことにも注意。
こうした現場でゲートキーパーに役割としての満足や自信が維持できるかは難しいように思う。
まとめ
メンタルヘルスに関連した、ゲートキーパー教育や知識啓蒙の全部にダメだしをするというのではないが、現場で役割を持った者の様々な困難やリスクと不安にも配慮しなくてはいけない。
また、ごく短期的な成果を求めすぎてもいけない。


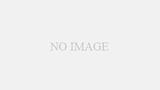
コメント