先日、勉強会で惨事後のグループミーティングをテーマにした。
(最近数回、このテーマで繰り返し続けている)
惨事後、関係する参加者が集まって出来事のふりかえりをすると、過覚醒状態も手伝って、特定の人物や組織、あるいはお互いに対する攻撃的な発言が見られることがある。
知識としてわかっていても、そうした言動やミーティングの場をファシリテートするのはロールプレイや現場で学ぶのがもっとも良い、というか他に方法はない。
一般的な会議やミーティングのファシリテーターとは違って、参加者のコミュニティ文化を熟知はしていない、参加者らが最初から友好的で協力的であるとは限らない、「ゴール」を設定するかしないか、設定するならばどんな落とし所にするかなど、かなりの臨機応変さが要る。
過覚醒的な言動が見られた時には、それを必ずしも否定したり、スルーしたりせずに、グループミーティングという「特殊な」場だからこそ(という態度で)参加者とファシリテーターが協働して扱うことがコツになる。
このコツ自体、現場どころか、ロールプレイトレーニングでも実践実行するのはやや難しい。
プラスして感じたのは、このような流れのファシリテートで大事なのはその最初の発言を直後に拾ってミーティングのテーマとして重要であることを参加者に示さなくてはいけないということだ。
タイミングが大事。
一度スルーしてしまえば、同じような発言、イライラした感覚などをナマのまま、正直に場に出すことのモチベーションは参加者全員から消え失せてしまう。
いったんそうなったら、そこからリカバリーするのはドンドン難しくなってしまう。
だから、「最初のタイミングを逃すな」という教訓が出てくるのだ。
一度、話の流れが上手くはかどらなくなってしまってから、あらためて仕切り直すということは個人に対するカウンセリングであれば、時間はかかってしまうができなくはない。
しかし、グループミーティングはファシリテーターの「ミス」が一気に参加者全員に伝わってしまう。
そして現実に再度、再々度のミーティングを設定することはまずないと思ったほうがいい。
この点はグループミーティングの難しさと、ファシリテートすることのプレッシャーとして認識しておこう。
2012-02-27 06:00


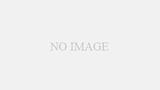
コメント